- ホーム
- 不妊カウンセラーが今気になる妊活・不妊のメディア情報
不妊カウンセラーが今気になる妊活・不妊のメディア情報
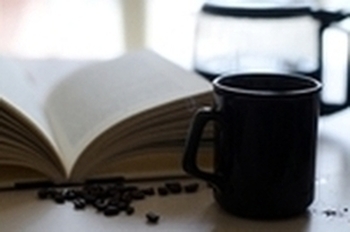
妊活・不妊治療に関する情報は、ここ最近メディアで取り上げられることも多くなってきました。
カウンセリングルームwithのアンテナがキャッチした情報を掲載していきたいと思っています。
新聞・ニュース・ネット・雑誌・本 さまざまなメディアからの情報をランダムにお伝えしていきます。
全てを網羅した情報とはなっていないことを事前にご了承ください。「不妊カウンセラーが今気になるメディア情報コラム」としてお楽しみください。
26回目 日本生殖心理学会 パンデミック委員会からの提言・情報提供 2020.5.15 日本生殖心理学会サイトより
2020/05/25
《26回目》 日本生殖心理学会 パンデミック対処委員会よりの提言・情報提供
日本生殖心理学会 パンデミック対処委員会が新型コロナの感染拡大の状況を受けて不妊治療にかかわる方々へ提言と情報提供をサイトで発表しました。
- 1.新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の流行拡大に際して
- 2.生殖医療従事者の皆様へ
- 3.コロナ禍で不安を抱えている不妊患者様へ
- 4.不妊当事者の皆様へ:心理的健康を保つために役立つこと
新型コロナウィルス感染症の流行拡大によって、メンタルヘルス上の問題を生じさせることが懸念されています。
不妊治療を利用してお子さんを望まれる方にとっては、日本生殖医学会から4月10日に出された声明で不妊治療の延期を推奨されたこともあり、今妊娠しようとすることが良いことなのか迷われたり、同時に見通しの立たない状況から時間が過ぎることが妊孕性(妊娠する力)の低下につながるのではないかとの不安も強くもたれているだろうということで、ストレスへの対処法などを提言したものです。
ただ、この「見えないもの」への不安や疑心暗鬼、不信感などが高まり、人との距離感や付き合いなども困難になっているコロナ禍の状況は、不妊を取り巻く状況とよく似たところがあり、これまでこの不妊状況を生き抜いてきた当事者にとっては対処の仕方はすでに知っていることであり、これまで取ってきた対処法が役に立つ時でもある、ということも言われています。
1.不確実な情報に踊らされない
2.一つだけの正解を求めない
3.「一人でいること」と「つながること」の両方を大切に
不妊の状況を生き抜いてきている当事者にとっては、コロナ禍の状況は、重なることでちょっとだけしんどい思いも増えるかもしれませんが、初めてのことのようなダメージは少ないことといえるかもしれません。
自分の気持ちが楽になるストレス解消法をどんどん実践して、あとすこし乗り切っていきたいものです。
25回目 もしも「距離を保つ」ことをもとめられたら 2020.3.23 日本心理学会サイトより
2020/03/24
《25回目》 もしも「距離を保つ」ことをもとめられたら
アメリカ心理学会が公式webに掲載した記事の翻訳。タイトルは、Keeping Distance to stay safe .です。日本語タイトルは「距離を保つことを求められたら」
感染予防のための、個人個人の距離の取り方や、それを求められたときの心理的な葛藤について。さらに、検疫や隔離のさいの、心理的な理解についても書かれています。
もしも距離を保つことを求められたら・・・
●何が起きるのか
恐怖と不安
抑うつと倦怠
怒り、フラストレーションやイライラ
スティグマ化
社会的弱者
人間は距離をとられると、自分自身が否定されたと感じやすく、そこで、上記のような心理的な葛藤が起こりやすくならるそうです。
頻繁にハグをしたり握手をしたりする文化がない日本でも、自宅や病院などにこもっていると不安は大きくなります。そうなってもそのことが決して自分自身の存在を否定されているわけではないことを理解しておきたいものです。また、他人に対してもそうであることを、相手にも知っておいてもらい自分でもわかっておきたいですね。
●どう対処するか
信頼できる情報を獲得しよう
日々のルーティンを作り、それを守ろう
他者とのヴァーチャルなつながりを保とう
健康的なライフスタイルを維持しよう
ストレスを管理し、前向きでいるために心理的方略を使おう
距離をとったとしても、気持ちを伝えあうことはできます。ヴァーチャルなつながりであっても、優しい声のトーンや笑顔などによってもそれは伝わっていきます。
また、日々のルーティンを作り、健康的なライフスタイルを維持するためにできることを実践していくことは、メンタルを健康に維持していく意味でもとても大切なことだと思います。
これが出されたのは4月の上旬。
改めて読み返すと、さらに書かれていることの大切さが実感されます。
悲しみや不安を感じている場合は、こうした方法で自分が経験したことや自分の気持ちについて話し合ってみてください。そして、似たような状況にある知り合いにも手を差し伸べましょう。SNSで、同じような隔離状況に置かれた人々同士で話し合い、互いに助け合うためのグループを作るのもよいでしょう。
FBやZoom、LINEなどが、あっという間に自分の周囲で盛んになってきています。
TVでは動物ものなどが多くなっているような気がしますし、自分自身もそういう映像にこころを癒されているような気がします。
また、その後に起こることとして、安堵の後の怒りや不安についても書かれています。
その後に起こること
隔離が終わると、安堵と感謝、あなたにウイルスを移されるかもしれないと恐れていた人々へのフラストレーションや怒り、さらには個人的な成長や精神性の向上といった、いくつもの入り混じった感情を持つかもしれません。不安を感じることもごく普通にあるでしょう。
自粛状態が長引いてきており、すでに怒りやフラストレーションがいろんなところへ向かって噴出されているなどのニュースも目にします。
もう少しと思っている自粛要請が伸びることになったら、さらに行き場のない不満やいらだちが増大していきそうにも思います。家の中で人に触れる機会のないままだと、自分一人だけがこんな思いをしているような気にもなってくると思います。
気持ちだけでも外に向けて、それぞれの家の中でも同じようなことが起こっているだろうと想像し、ヴァーチャルでもよいので実際につながってみて、同じ思いであることを確認することはとても大切だと思います。
リアルに人と会えること、何気ないおしゃべりが大切な役割をしてくれていることをしみじみと感じる今日この頃です。
24回目 16人に一人が体外受精児 17年、5万6千人誕生 2019.10.29 日本経済新聞
2019/10/03
《24回目》 16人に一人が体外受精児 17年、5万6千人誕生 2019.10.29 日本経済新聞
不妊治療の体外受精によって2017年に誕生した子どもの数は、5万6617人だったとの調査結果を日本産婦人科学会が29日までにまとめた。この年に生まれたこどものおよそ16人に1人の割合。最多だった16年の5万4110人を2500人余り上回った。
毎年日本産婦人科学会で発表されている、体外受精の実施件数、総治療周期数などの数値が出ました。
団塊ジュニア世代が40代となり、治療者数が減り治療件数も減るのではとの予想でしたが、2016年をわずかに上回る数値となりました。
またこの数値は、新鮮胚移植、凍結胚移植別に算出されていたり、年齢別の実施件数なども読み取れます。
2017年新鮮周期と凍結周期別に治療されている年齢別の数値が出ています。見ていると私は最高齢に目が行きました。
この表は昨年までは表示おらず今年からの提示ですが、これまでの年の数値も一緒に発表されています。
2017年の採卵された方の最高齢は58歳。出産されている方の年齢だと、新鮮周期では47歳。凍結周期では50歳です。
驚いたのは、2016年には採卵された方の最高齢は60歳で、出産は、新鮮周期ではおなじく47歳ですが、凍結周期では53歳の方がいらっしゃったことです。
出産までの数値ですし、赤ちゃんの様子や産後の状況などは全くわかりませんが、あれこれと思いを馳せてしまいます。
同時に治療周期総数の448,210件に対し、出生児数は56,617人。出産に至らなかった30数万もの治療周期に流れた涙のことにも思いを馳せています。
※日本産婦人科学会で調査を行っている日本国内での治療数、年齢別の治療成績は下記のサイトから見る事が出来ます。
22回目 不妊治療する女性 5人に1人が退職・・・仕事との両立 真面目な人ほど苦しむ 2019.7.25 ヨミドクター(読売新聞サイト)
2019/07/29
《22回目》 不妊治療する女性 5人に1人が退職・・・仕事との両立 真面目な人ほど苦しむ 2019.7.25 ヨミドクター(読売新聞サイト)
読売新聞の医療・健康・介護サイトのコラム「いつか赤ちゃんに会いたいあなたへ」の記事です。
NPO法人Fine〜現在・過去・未来の不妊体験者を応援する会〜の理事長である松本亜樹子さんが書かれてます。
今回のコラムでは、今現在も変わらぬ課題である「不妊治療と仕事の両立」についてお伝えしたいと思います。~中略〜(NPO法人Fineが実施したアンケートでも)「本格的に不妊治療をはじめることになったので退職した」「体外受精に進むことになったので、仕事を辞めた」というコメントはいくつもみられました。
もちろん、事前にやめる人の方が少数派で長引くにつれて両立が難しくなり、泣く泣く仕事をやめた」という人が大半です。しかしいずれにしても共通していることは「真面目に頑張っている人ほど、両立に苦しんでいる」ということです。もしかしたらどちらかを適当に考えることができれば、もう少しやりやすいかもしれないのに、どちらも一生懸命に頑張ろうとするあまり、ギリギリまで張りつめて、ある日ポキンと音を立てて折れてしまうように私には感じられます。
私は前者で、事前にやめてしまった派です。
でもたしかに後者のようにぎりぎりまで頑張って「両立が難しい」おっしゃってカウンセリングに来られる方は多いです。
決して不妊治療を特別扱いしてほしいと思っているわけではありません。不妊は表出しづらい課題であるため、ダイバーシティ&インクルージョンの中にあらかじめ「不妊」や「不妊治療」という視点を一つ足していただきたい、ということなのです。
厚生労働省は今年度、不妊治療と仕事の両立支援のために初めて企業に対して働き掛けることが明らかになりました。両立を支援するための企業向けマニュアルそ策定する方針を発表されたのです。できるだけ辞めずに済むように、との支援を活用しない手はありません。
「仕事は続けたい、けど現状無理ではないか・・・」と思い悩んでいる場合は、あきらめないでできることは無いか考えてみていただけたらなと思います。
【関連サイト】
NPO法人Fine 「不妊白書」 http://j-fine.jp/activity/hakusyo/index.html
21回目 14歳の帰り道、車でさらわれた。あれが「魂の殺人」だと、今の私は思わない 2019.6.11 Yahooニュース
2019/06/13

《21回目》 21回目 14歳の帰り道、車でさらわれた。あれが「魂の殺人」だと、今の私は思わない 2019.6.11 Yahooニュース
いつもは、不妊治療に関する記事を掲載しているコーナーですが、今回は自伝を出された方のインタビュー記事です。
性被害にあわれた方なのですが、その経験の受け止め方、その後の人生の切り開き方、考え方にとても共感を覚えたので取り上げてみました。
国際政治学者の三浦瑠麗さんが、過去に受けた性暴力や長女の死産の経験を綴った自伝を出版した。孤独だったこと、傷ついたこと、それが自分の人生にどんな意味を持ってきたのかということ。【BuzzFeed Japan/小林明子】
性被害について書かれた本ではないとインタビューで答えていらっしゃいます。
ただ、自分の人生の中で、どのような体験として位置付けてきたのかを、どうやったら読者の方々に伝えられるかについては、よく考えました。
魂の殺人だと思っていいし、私もそう思い込んで消えてしまいたかった時期もあります。でも、それは社会の通念や価値観をそのまま受け入れていたからでもあるし、そのときに理解してくれる人が現れなかったからでもあるんです。
(中略)
被害者としてのみ生きてきたわけではありません。
たしかに暴行事件は陰惨なものでした。私の場合は特に。でも、比較にならないくらい、その後の人生のほうが豊かであり、かつ痛みも伴ったし、ずっと手応えがあったよ、ということなんですよね。そういう中で得てきた経験を、本を書くことで差し出すということは、別に、強さの表明ではないと思っています。
(中略)
母親にしても男性たちにしても、私と同じ経験をしていないからわからないだろうという諦めもある一方で、いくばくかの理解を求める気持ちもあるわけです。それなのに、相手から想定外の回答が返ってきたり、あるいはもはや自分がそんな無理解に慣れっこになっている中でも同じ反応ばかりが続いていけば、絶望を深めるじゃないですか。
こういうとき、社会を責めるのは簡単です。でも人間というのはお互いに無理解な存在です。性暴力被害者に限らず、孤立を感じる人間はたくさんいます。
私は、すべてを自分で消化することでしか救われなかったんです。
同じ経験をしていないからわからないだろうという諦めと、いくばくかの理解を求める気持ち。
それは不妊治療に関して周囲の人に抱く気持ちと同じです。無理解にさらされるたびに絶望に陥ってしまい孤独を感じていくのも同じ構図だと思います。
すべてを自分で消化するしかない、と三浦さんはおっしゃっていますが、一人で考え続けることはつらい作業でもあります。だれかと分かち合えたら、誰かの考えや生き方を参考に出来たら、それに従っていけばいいのでは・・・そう思ってしまうのも当然だと思います。
それでも、「誰にでも通用する解決策やハウツーなんて存在しない」と三浦さんも述べているように、人の生き方にそういうものは無いと私も思います。
一般論や通説に落とし込まない体験、経験、生きざまに触れて、照らし合わせながらもなお自分なりのの生き方に落とし込んで考えていき形作っていくしかないのだと思います。
この本、ぜひ読んでみたいと思っています。
三浦瑠麗 著「孤独の意味も、女であることの味わいも」 新潮社
with
 妊活・不妊カウンセリング/心理カウンセリング
妊活・不妊カウンセリング/心理カウンセリング
つらさや生きづらさをひとりで抱え込んでいませんか。ひとりで悩まないでご相談ください。
電話番号:090-9681-3630
★オンラインカウンセリングにも対応可能。全国・海外からもお申し込みできます。
所在地 :福岡市内
営業時間:火曜 9:00〜18:00 土曜(月2回程度) 10:00〜17:00
定休日 :日曜日

